
住宅購入は家庭を持った方の一番大きな夢ともなりますが、高額購入となるためそうやすやすと購入に踏み切れるものではありません。しかも、何十年にも渡る住宅ローンを組むことになるので、将来を見据えたローン組も必要となってきます。
そこで一番気になってくるのが新築マイホームを購入する際に必要な住宅ローンの借入金額。この額によって返済年数や毎月の返済額が変わってくるので、どれくらいの借り入れが必要となるのかは重要なポイントとなってきます。
そこで今回は新築マイホームを購入する際に必要な住宅ローンの借入金額はいくら必要なのかを検証していきましょう。
新築住宅の価格推移
新築マイホームを購入するのに一括購入できる人はごく一部の富裕層のみで、その大半が住宅ローンを組んでの購入となります。よって将来を見据えた返済に無理のないローンを組むことが重要なポイントとなってきます。
となれば毎月のローン返済に大きな影響を及ぼす新築マイホームの購入価格はどれくらいが適正価格となるのかを知っておかなければなりません。できるだけ希望にあった新築マイホームを購入したいのは分かりますが、収入に見合った物件購入でないとあっという間に返済不能に陥ってしまいます。
よって妥当な返済額に応じた新築マイホームの購入価格を知ることが一番重要となってくるのです。
近年はマイナス金利の影響により住宅ローン金利が引き下げられたことから、住宅購入者は年々増加傾向にあると言われています。となれば低金利の影響によって購入物件の価格も上昇しているのでしょうか?
今までは購入できなかった高額物件も低金利の恩恵によって購入できる可能性が出てきたので、これは十分に考えられることでしょう。しかし、逆に金利恩恵をそのまま購入金額に反映させるため敢えて高額物件を避けるという考えもあります。
そこで近年の新築住宅の価格推移を見ていきながら、市場動向はどうなっているのかを検証していくことにしましょう。
新築一戸建ての価格推移
国土交通省が平成29年3月に発表した平成28年度の「住宅市場動向調査報告書」によると、新築住宅建築資金と建替住宅建築資金の推移は下記のようになります。
新築住宅建築資金の推移
- 平成24年 2,885万円
- 平成25年 2,843万円
- 平成26年 2,958万円
- 平成27年 2,951万円
- 平成27年 3,082万円
建替住宅建築資金
- 平成24年 2,925万円
- 平成25年 3,012万円
- 平成26年 3,245万円
- 平成27年 3,072万円
- 平成27年 3,249万円
建替住宅建築資金の方が若干高額とはなりますが、新築住宅の場合は建築資金に加えて土地購入資金が必要となるケースが少なくありません。
その土地購入資金の推移は下記のとおりです。
- 平成24年 1,360万円
- 平成25年 1,351万円
- 平成26年 1,373万円
- 平成27年 1,300万円
- 平成27年 1,224万円
となれば新築住宅を購入するには、実質は下記費用が必要となっているのです。
- 平成24年 4,245万円
- 平成25年 4,194万円
- 平成26年 4,331万円
- 平成27年 4,251万円
- 平成27年 4,306万円
つまり、新築住宅購入価格は、土地購入費用のあるなしで住宅価格は1,000万円ほどの価格差が出てきますが、土地購入の必要がないなら3,000万円前後、必要があるなら4,000万円台前半が市場価格となってきます。
新築分譲マンションの価格推移
それでは次は新築分譲マンションの価格推移を、先程と同じ平成28年度の「住宅市場動向調査報告書」から見ていくことにしましょう。その結果は下記のとおりです。
- 平成24年 3,400万円
- 平成25年 3,583万円
- 平成26年 3,636万円
- 平成27年 3,903万円
- 平成27年 4,423万円
新築分譲マンションの価格は平成24年に前年度より30%もの上昇を見せ、その上昇幅は年を追って増大しています。これもあってか4,000万円台に届こうかという平成27年度から売れ行きが鈍くなり始め、4,000万円台に突入した平成27年度には一段と低迷しています。
現状は土地購入費用込みの新築住宅購入価格と遜色ない価格となっていることも影響してか、現状は購入する時期ではないと判断する人が増加しているのが実情でしょう。
借入する際のポイントと金額推移
住宅購入で是非とも利用したいのが住宅ローン減税。この制度は住宅の新築購入や増改築時にかかった費用に応じて、一定の割合を所得税から控除してもらえる減税制度です。
高額な住宅費用も住宅ローン減税で軽減できる!
適用条件は下記のとおりとなり、中古物件購入が適用外という点が最大の特徴と言えるでしょう。
- 新築の住居購入、または増改築を行う人
- 住宅ローンの返済期間が10年超えであること
- 住宅の購入、増改築後の6ヶ月以内に入居し、年度末まで引き続き居住していること
- 控除受ける年の所得が3,000万円以下であること
現在、住宅ローン減税は2017年末まで延長されており、その概要は下記の通りとなります。
- 控除期間 10年間
- 各年の控除率 住宅ローン借入の年末残高×1.0%
- 住民税からの控除上限総額 4,000万円
- 住民税からの最大控除額 13万6,500円
- 一般住宅の最大控除額 400万円
この住宅ローン減税を利用することで高額となる借入額負担を軽減することができ、中古物件よりも新築物件を安く購入できる可能性も出てくるのです。
借入金額の推移
それでは実際に新築マイホームの住宅ローン貸出額の価格推移を見てみましょう。
下記調査結果は平成29年3月に国土交通省住宅局より発表されたもので、下記調査対象先のアンケートによって集計されています。
- 国内銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行など)
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 農業協同組合
- 生命保険会社
- 損害保険会社
- ノンバンク(モーゲージバンク等)
平成24年度から平成27年度までの新築マイホームの建設・購入等にかかる個人向け住宅ローン実績の推移は下記のとおりです。
- 平成24年 84,492億円(借入件数369,886件)
- 平成25年 81,262億円(借入件数352,727件)
- 平成26年 74,413億円(借入件数305,749件)
- 平成27年 74,870億円(借入件数285,424件)
上記の結果から分かるように新築マイホームの建設・購入等にかかる個人向け住宅ローン実績は貸出金額・件数ともに年々減少傾向にあります。また今回の主題となる1件当たりの借入額の平均は下記の通りとなります。
- 平成24年 2,284万円
- 平成25年 2,303万円
- 平成26年 2,433万円
- 平成27年 2,623万円
2,000万円大で推移しているのは変わりませんが、借入額は毎年100万円ほどの上昇傾向が見られます。
住宅購入費は年収が1つの目安に!
冒頭でも言いましたが住宅ローンを組む際に重要となってくるのが住宅ローンの借入金額。この額面によって返済年数や毎月の返済額が大きく左右されるので、自分の年収とバランスのとれた無理のない借り入れを行わなければなりません。
そこで1つの指標となってくるのが「借入金額 = 年収の5倍程度」です。この指標によって導き出された数値が余裕を持って返済できる借入金額とされています。
国税庁が平成29年9月に発表した平成28年度分のデータによると、日本人の平均年収は約420万円で年収の推移は下記のとおりとなっています。
- 平成24年 408万円
- 平成25年 413.6万円
- 平成26年 415万円
- 平成27年 420.4万円
- 平成28年 421.6万円
またこれをさらに細かく住宅購入する人の多い30代と40代の平均年収を見てみると下記のようになります。
- 30歳~34歳 403万円
- 35歳~39歳 433万円
- 40歳~44歳 460万円
- 45歳~49歳 494万円
この年収から先ほどの「借入金額 = 年収の5倍程度」を指標とし、購入可能な住宅価格を算出すると、先程挙げた1件当たりの借入額の平均も妥当なものであることがよくお分かりいただけるでしょう。
- 30歳~34歳 2,015万円
- 35歳~39歳 2,165万円
- 40歳~44歳 2,300万円
- 45歳~49歳 2,470万円
つまり、住宅購入における借入額は年々増加傾向にはありますが、大幅な増加は見られず、「借入金額 = 年収の5倍程度」を指標とした範囲内であると結論づけられるのです。
近年の借入額の上昇はマイナス金利の影響による住宅ローン金利引き下げが大きく影響していると考えられますが、上昇幅はその金利恩恵による範囲内に抑えられており、決して度を越した借り入れは行われていないのが実情と言えるでしょう。
新築住宅購入には頭金が必要?
今回説明したように新築住宅の購入には、3,000万円~4,000万円ほどの費用が必要となるのが実情です。しかし、この高額な購入費用もすべてを借り入れで補っているわけではありません。
住宅購入に当たっては自己資金が当てられることが大半です。俗に言う頭金がそれに当たるのですが、平成28年度の場合なら新築住宅建築資金の自己資金比率は27.3%、土地購入資金では45.0%となっており、実質の借入金額は2,912万円となっています。
そしてこの自己資金比率の割合は建替住宅建築資金の場合はさらに高くなり、平成28年度の場合は64.0%にも上り、実質、借り入れするのは1,169万円に抑えられています。また新築分譲マンションの場合も同様です。平成28年度の自己資金負担率は39.1%となっており、実質借入は購入費用4,423万円に対して2,694万円となっています。
今回説明した住宅購入費は決して「借入金額 = 年収の5倍程度」を指標とした範囲内に収まるものばかりではありませんが、頭金を用意して自己資金負担率を上げることでこの指標に近づけることができているのです。
近年はフラット35の登場により頭金ゼロで住宅ローンを組むことができるようになりましたが、実際のところは頭金を用意してから住宅購入を行う方が大半です。できるだけ満足のいく住宅購入をするためにも、やはり頭金を用意するのは重要なポイントとなってくるでしょう。

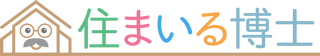

 家を購入する人は要チェック!資金計画書の注意点
家を購入する人は要チェック!資金計画書の注意点
 無理なく住宅ローンを組むため、知っておきたいこと
無理なく住宅ローンを組むため、知っておきたいこと
 都心部で利用者が多い「ペアローン」と「収入合算」の違いを知ってますか?
都心部で利用者が多い「ペアローン」と「収入合算」の違いを知ってますか?
 年収○○円だといくらくらい借りれるの?
年収○○円だといくらくらい借りれるの?
 優遇金利のメリット・デメリットは?適応させるに方法は?
優遇金利のメリット・デメリットは?適応させるに方法は?