
夢にまで見たマイホーム購入。しかし、そのマイホームは欠陥住宅だった。実は、こんな話は珍しいものではないのです。
現在、1年間の住宅着工件数は約100万件と言われていますが、国民生活センター等へ寄せられる欠陥住宅に関する相談は年々増加傾向にあり、その数は年間10万件とも言われています。
つまり、単純計算で新築物件10棟に対して、1棟のペースで欠陥住宅が発生しているということなのです。となればこれから住宅建設を検討している方には、決して他人事とは言えないでしょう。しかも、欠陥住宅だからといって住宅ローンの支払いが免除されるわけでもありません。
「じゃあどうすればいいの?」となってしまいますよね。そこで今回は欠陥住宅だった場合、どう対応すればいいのかを分かりやすく説明します。
そもそも欠陥住宅ってなに?
そもそも欠陥住宅とはどのような住宅状態を指すのでしょうか?欠陥住宅をめぐるトラブルでは、起こった不具合をすべて欠陥住宅と決めつけ建築業者に詰め寄る建築主をよく見かけます。しかし、欠陥住宅として扱うべき問題と、それ以外の軽微な問題とを混同して話を進めると効果的な交渉は行えません。
よって、交渉時には購入した住宅に見られる問題が本当に欠陥なのかどうかを建築主がよく理解しておく必要があるのです。一般的に欠陥住宅とは下記の問題が生じた住宅を指します。
- 建物が最低限備えるべき構造耐力上で重要な性能をもつ部分に問題がある
(例:基礎、柱、筋交い、床、屋根、はりなど) - 備えておくべき基本的な使用機能に問題がある
(例:雨漏りなどの水回りの問題を生ずる屋根、外壁、配管や床の傾斜など)
欠陥住宅の認定基準は法律上で明確な定義がないため、建築主や建築業者という立ち位置でその認識は違ってきます。よって交渉が水掛け論とならないためにも、ある程度の具体性や客観性を持った判断基準が定義化される必要があります。
それに当たるのが上記2つの定義です。基本的には住宅としてあってはならない重大な不具合が生じているかが、欠陥住宅であるかないかを判断するひとつのボーダーラインとなってくると考えておけばいいでしょう。
具体的事例から見る欠陥住宅
しかし、建築業者でもない素人の建築主がこの定義2つだけをもって、欠陥住宅かどうかを判断することは難しいのが実情です。そこで欠陥と判断できる具体的な事例を挙げていくことにしましょう。
欠陥住宅と見極める具体的事例は2つに分けられる
「欠陥住宅だ!」と騒ぎ立てるのは実際に問題が生じていからが多いのですが、欠陥住宅は先に説明したような構造上の問題を既に抱えているので、まだ目に見えない将来的不具合の発生する潜在的欠陥が隠れています。
よって、欠陥には具体的な問題が発生しているものと、まだ発生していない潜在的なものの2つに分けることができます。
具体的な問題が発生しているもの
- 床が明らかに傾斜している
- 基礎の一部が沈んでいる
- 壁や柱に傾斜が見られる
- 雨漏りがする
- 配管等から水漏れがあり、壁や床等にシミ跡が見られる
- 著しく結露の発生が見られる
- 終日換気量が不足している部屋がある
発生していない潜在的なもの
- 土台等に防腐防蟻の対策措置が取られていない
- 耐震部材の不足や適切な設置が行われていない
- 耐震部材が決められた規格や設置基準に適合していない
- 基礎深部が地盤の凍結深度に達していない
- 基礎のコンクリート厚が足りていない
- 外壁に準防火構造設定仕様に定められた以外のものが使用されている
これら具体的事例を見てもらえればわかるのですが、実際に欠陥が具体的な問題として発生している場合は誰でも簡単に判断できますが、まだ問題として発生していない場合には、素人では全く判断がつかないものばかりです。
具体的な問題として現れてから欠陥住宅だと騒ぎ立てる方が多いのも、建築主が発生していない潜在的な欠陥を判断するだけの知識がないことが原因でしょう。しかし、本当に欠陥住宅ならば欠陥が問題となって現れるより、前の段階で対応した方が被害は少なくて済みます。
よって、少しでも欠陥住宅かもという懸念があるのならば、早めにその是非を確認する必要があるのです。
欠陥住宅を見分ける方法は?
先に言ったように欠陥住宅は既に何らかの問題として症状が現れているなら、「具体的な問題が発生しているもの」で説明した具体的事例に照らし合わせれば簡単に判断できますが、発生していない潜在的なものに関しては素人では簡単に判断できません。
しかし、発生していない潜在的な欠陥は何らかの予兆を見せていることが大半です。よって、その予兆を見つけることで潜在的な欠陥を見つけ出すこともできます。その予兆とは下記のような症状です。
- 屋根裏に雨ジミが見られる
- 壁等にひび割れや亀裂がある
- 窓やドアの開閉がスムーズに行えない
- 歩くと不自然な浮き沈みを感じたり、キシミがある
- 床に置いたボールが勢いよく転がる
- 床に置いたペットボトルの水が揺れる
住宅にこれら予兆が確認できれば現状で大きな問題がなくても、いずれ「欠陥住宅では?」と心配しなければならない問題が現れる確率は高いと言えます。よって、これら予兆が確認できたならば、本当に欠陥があるのかを専門業者に調査してもらうことをおすすめします。
専門業者の専門調査ならば欠陥の真偽はハッキリしますし、専門業者でしかわからない潜在的欠陥も見つけ出すことができます。欠陥住宅による問題が大きくならないうちに適切な対応を行うためにも、早めに調査依頼することをおすすめします。
また今回紹介した欠陥住宅を見分ける方法は何も購入後だけに利用できるものではありません。欠陥住宅の被害を避けるためには、欠陥住宅を購入しないことが最善策となります。
よって、建売を購入する場合には、まず自らこれらの方法での事前調査をしてみましょう。周りには変な目で見られるかもしれませんが、購入後に大変な思いをすることを考えれば何でもないことです。
購入前には必ず自分の目で事前調査し、少しでもおかしいと思ったら購入は避けるようにしてください。
専門業者に掛かる費用は?
専門業者に欠陥調査を依頼する場合には、当然ですが費用が発生します。一般的な相場は予備調査と本調査で10万円~15万円といったところで、住宅の大きさに合わせて「1800円/㎡ × 延床面積」で計算するところもあります
決して安価な費用ではありませんが、建築業者との交渉を優位に進めるためにも、専門業者による専門性の高い調査結果は必要です。この点をよく理解して、専門業者による調査は必ず行うようにしましょう。
欠陥住宅だった場合の補償はどうなるの?
購入した住宅が欠陥住宅だった場合、1番気になってくるのが補償でしょう。住宅ローンは購入物件が欠陥住宅だからといって、免除されたり減額されたりすることはありません。契約通りに完済まで支払う義務があるのです。よって、修繕費まで背負わされたのではたまったものではありません。
ですが欠陥住宅だった場合には、受けられる補償が存在します。それが瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)です。
瑕疵担保責任とは?受けられる補償は?
瑕疵担保責任なんて難しい言葉を言われても、何のことやら分からない方も多いでしょう。これは簡単に説明すると「売ったものに事前に分からなかった故障があれば、それに対して損害賠償などの責任を負う」という意味です。
瑕疵担保責任は民法と宅建業法に定められた法律で、売主が買主に対して販売したものに「知らなかった」「見つからなかった」という大きな問題あった場合に責任を負うことを義務付けています。
そして住宅への瑕疵担保責任は、建築業者へ下記期間内における修繕や補償が義務付けているのです。
- 新築物件:引渡しから10年以内
- 中古物件:引渡しから2年以内
よってこの期間内であれば、欠陥住宅とわかってもそれを無償で修繕してもらうことができます。瑕疵担保責任で修繕や補償の対象となるのは、先に欠陥住宅の一般的な定義であると説明した下記の2つです。
- 建物が最低限備えるべき構造耐力上で重要な性能をもつ部分
(例:基礎、柱、筋交い、床、屋根、はりなど) - 備えておくべき基本的な使用機能
(例:雨漏りなどの水回りの問題を生ずる屋根、外壁、配管や床の傾斜など)
これ以外は瑕疵担保責任が適用されないので、住宅に発生した問題の原因が何にあるのかを正確に特定してやる必要があります。となればやはり専門業者による正確な調査は欠かすことができませんね。
欠陥住宅だと思ったら素早い対応を!
欠陥住宅と判明したら素早い修繕が必要になります。時間が経てば経つほど欠陥が住宅に及ぼす問題は深刻となり、住む方の生活にも悪影響を及ぼすことになるからです。
しかも、瑕疵担保責任は永久的ではなく、責任期間が決められています。よって、満足のいく状態まで修繕しようとしても、責任期間が過ぎていたため自費修繕となる可能性もあるのです。
欠陥住宅かなと思ったらその真偽をすぐに明らかにし、建築業者と交渉を進めて今後の対応を決めるようにしてください。

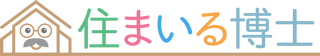

 家を購入する人は要チェック!資金計画書の注意点
家を購入する人は要チェック!資金計画書の注意点
 無理なく住宅ローンを組むため、知っておきたいこと
無理なく住宅ローンを組むため、知っておきたいこと
 都心部で利用者が多い「ペアローン」と「収入合算」の違いを知ってますか?
都心部で利用者が多い「ペアローン」と「収入合算」の違いを知ってますか?
 年収○○円だといくらくらい借りれるの?
年収○○円だといくらくらい借りれるの?
 優遇金利のメリット・デメリットは?適応させるに方法は?
優遇金利のメリット・デメリットは?適応させるに方法は?