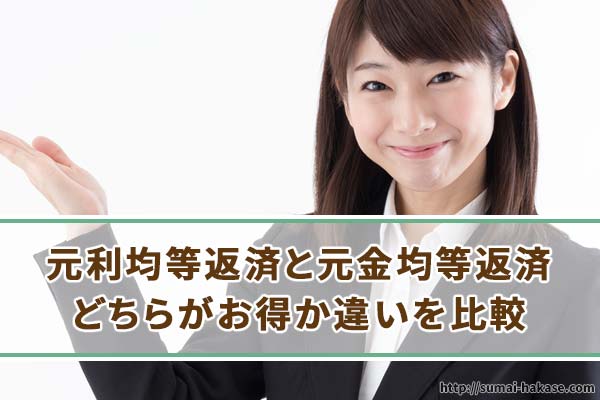
住宅ローン選びには金利タイプの選択も重要ですが、まず決めなくてはならないのが返済方法。現在、住宅ローンの返済方法は下記の2つがあり、どちらを選択するかによって受けられるメリット・デメリットが違ってきます。
- 元利均等返済
- 元金均等返済
そこで今回はどちらの返済方法がお得なのかに焦点を絞り、それぞれのメリット・デメリットを見ていくことにしましょう。
返済方法とは?
返済方法と言われてもピンとこない人も多いのでは?住宅ローンの返済は借り入れした元金だけでなく、それにかかってくる利息の支払が発生します。この利息がどちらの返済方法を選ぶのかによって大きく違ってくるのです。
そこでまずは今後の説明をよく理解してもらうためにも、返済方法について簡単に説明しておくことにします。
毎月の返済額の算出方法
それではまず返済方法に大きく関係してくる利息は、どのようにして発生するのかを説明します。毎月の返済で発生する利息額は常に同じではありません。借入残金に応じて発生する利息額は違ってくるのです。
その利息額は下記の計算式で求められ、借入残高が少ないほど発生する利息は少なくなるという特徴を持ちます。
借入残高 × 金利 ÷12ヶ月
よって金利1.0%で3,000万円の住宅ローンを組んだ場合、初回返済で発生す利息は下記のとおりとなりますが、
3,000万円 ×1.0% ÷ 12ヶ月 = 2.5万円
二回目の返済時には初回返済で元金が返済され借入残高が減ったため、発生する金利は下記のように変化します。(元金返済額を2.5万円とした場合)
(3,000万円-2.5万円) ×1.0% ÷ 12ヶ月 = 2.49万円
若干ではありますが発生する利息が少なくなったことが分かりますよね。住宅ローンで発生する毎月の利息額は借入残金が多ければ多いほど高額になり、少なければ少ないほど少額となるのです。
住宅ローンは借入額が高額になるため返済負担を減らすためには、毎月発生する高額な利息にどう対応するのかがひとつのポイントとなってきます。毎月の返済額に占める「元金返済額」と「利息支払額」のバランスをどう設定するのかで支払う総利息額が違ってくるというわけです。
そこで問題となってくるのが2つの返済方法。元利均等返済を選ぶか、元金均等返済を選ぶかでこのバランスが大きく変わり、支払う総利息額も大きく影響することになります。
それでは返済方法について理解してもらったところで、実際にこれら2つの返済方法について検証していくことにしましょう。
元利均等返済とは?
元利均等返済は住宅ローンで用いられる最もポピュラーな返済方法で、毎月決まった額を返済します。毎月の返済額が定額なため、返済予定が立てやすいのが一番の特徴と言えるでしょう。
それでは元利均等返済のメリット・デメリットを見ていくことにしましょう。
元利均等返済のメリット
元利均等返済のメリットとして挙げられるのは、あとで説明する元金均等返済と比較してのメリットの意味合いが強くなってきます。先ほどのデメリットのように返済方法自体が生み出すものではないのですが、返済方法を選択する際には重要なポイントとなってきます。
そのメリットは下記のとおりです。
- 返済額が一定のため返済計画が立てやすい
- 元金均等返済よりも借入当初の返済額が少ない
元利均等返済に比べると返済額が常に一定であることから返済計画が立てやすく、当初返済額は少額で済みます。返済期間の長期化に伴う支払う利息総額の高額化という支払い面でのデメリットはありますが、その代わり支払いに窮することのない安定した返済を行えるメリットが生み出されています。
長期返済と高額借入を伴う住宅ローンにおいては、無理なく安定した返済が行えるのは見逃すことのできない大きなメリットとなってくるでしょう。
元利均等返済のデメリット
元利均等返済の仕組みは毎月発生する利息に応じて返済する元金を調整します。つまり、発生する利息が高ければ返済する元金は低くなり、その逆ならば利息は低くなり、返済元金は高くなります。
よってこの返済方式は、下記のようなデメリットを生み出すことになるのです。
- 当初の元金返済額が少額となる
- 元金均等返済よりも返済期間が長くなる
先程、利息が発生する仕組みについて説明したとおり、利息は借入残高が多ければ多いほど高額となります。よって、借入残高が多い初回返済時には発生する利息が高額になるため、毎月の返済額を定額にする元利均等返済では、返済額に充当される元金返済が最初の方はどうしても少額となってしまいます。
また元金返済に充てられる返済が少額になれば元金の減りはその分、長くなってしまいます。
元金返済額が少額であるということは、元金がなかなか減らないということを意味します。となれば必然的に返済期間はどうしても長くなってしまい、支払う総利息額は自ずと高くなってしまうのです。
よって元金が減っていなローン開始当初は高い利息が発生するため、元金返済が進まずどうしても返済期間の長期化を招くことになります。
借入額が高額となる住宅ローンでは高額利息による影響は顕著に現れてきます。借入額が高額なため発生する利息は高くなり、さらに返済する元金が少額になることで高額な借入残高はなかなか減らないデメリットを生むことにいなるのです。
元金均等返済とは?
元金均等返済は決まった元金返済額に、発生する利息を上乗せしたものが毎月の返済額となります。よって返済により元金が減ることで毎月の返済額が変動してくるので、毎月定額の返済が行える元利均等返済とはまったく違った返済方法となります。
しかし、元金返済額を定額とすることで確実に元金返済が行えるので、元金返済が元利均等返済よりも早く進むという大きな特徴を持ちます。
それでは元金均等返済のメリット・デメリットを見ていくことにしましょう。
元金均等返済のメリット
元利均等返済のメリットは下記のとおりです。
- 毎月確実に元金返済が進められる
- 同じ返済期間ならば元利均等返済よりも支払う総利息額が少なくなる
それではこれら2つのメリットについて詳しく説明しましょう。
確実に元金返済が進められる
元利均等返済の場合は毎月の元金返済額は発生する利息に左右されることになります。しかし、元金均等返済はあらかじめ毎月返済する元金が決められているので確実に元金返済を進めることができます。
これは元金均等返済の一番のメリットであり、特徴といえるでしょう。
元利均等返済で毎月の返済額を10万円とし、初回に発生する利息を2.5万円としましょう。この場合は元金返済額は否応なしに7.5万円に設定されてしまいます。
しかし、元金均等返済で元金返済を毎月8万円に設定しておけば、「8万円 + 2.5万円 =10.5万円」と返済額こそ元利均等返済よりも大きくなりますが、確実に多くの元金返済を行うことができます
たった5千円の差と思うかもしれませんが住宅ローンは何十年という長期ローンとなる上、可能であれば元金返済額を増やすことでさらに大きな差を生むこともできるのです。
元利均等返済より支払う総利息額が少ない
いま説明してように元金均等返済のメリットである確実に元金返済ができる点は、元利均等返済と比較すると確実に支払う総利息額の差を生み出します。
下記の条件でそれぞれ総額いくらの利息が発生するのかをシミュレーションしてみましょう。
- 借入金額3,000万円
- 固定金利1%
- 返済回数360回(30年)
- ボーナス返済なし
*融資手数料や保証料等の諸費用は0円で計算しています
それぞれの結果は下記のとおりです。
(元利均等返済の場合)
- 総返済額 34,736,760円
- 発生利息 4,736,760円
(元金均等返済の場合)
- 総返済額 34,512,180円
- 発生利息 4,512,180円
今回は詳細を省いたシミュレーションとなりますが、それでも元金均等返済の方に20万円以上もの利息減額が生まれています。
同じ返済期間で考えた場合、できるだけ利息支払いの負担を減らしたいと考えるならば、元金均等返済に軍配が上がるのは明らかですね。
元金均等返済のデメリット
元利均等返済はいま説明した支払う利息面ではメリットを生みますが、それでも元利均等返済の方がポピュラーな返済方法となっているにはわけがあります。それはまさに元金均等返済がもつデメリットが影響していると言えるでしょう。
そのデメリットは下記のとおりです。
- 返済当初の返済額が元利均等返済より高くなる
- 激変緩和措置を受けられない
それではこれら2つのデメリットについて詳しく説明しましょう。
返済当初の返済額が元利均等返済より高くなる
先程メリットで説明したように元金均等返済の毎月の返済額は、定額元金に借入残高に応じた利息が加算されたものになります。
よって、返済当初は借入残高が高額なため、発生する利息も高くなるので、毎月の返済額は定額の元利均等返済より高くなってしまいます。
下記の条件でそれぞれの初回返済額がいくらになるのかをシミュレーションしてみましょう。
- 借入金額3,000万円
- 固定金利1%
- 返済回数360回(30年)
- ボーナス返済なし
*融資手数料や保証料等の諸費用は0円で計算しています
それぞれの結果は下記のとおりです。
- 元利均等返済 96,481円
- 元金均等返済 108,333円
前回のシミュレーション同様に詳細な計算ではありませんが、上記のように毎月の返済額には1万円以上もの差が出ています。この差額の大小の判断は個人の判断によるところとなりますが、元金の返済が大きく進む中盤以降までは毎月の返済額は元利均等返済より高くなります。
多くの元金返済を行うツケが毎月の返済額に反映されているのです。
激変緩和措置が受けられない
変動金利は金利が激変した際の保護措置として下記内容の激変緩和措置が設けられています。
- 金利変動があっても5年間は据え置き
- 金利変更後も上昇率は1.25倍が上限
変動金利は金利が上昇すればすぐにでも金利が変更されると考えている人もいるようですが、実際には上記措置によって、その煽りをまともに食らうことから保護されているのです。
ですがこの激変緩和措置を受けるには、返済方法に元利均等返済を選ぶ必要があります。元金均等返済の場合にはこの措置の適用が受けられず、金利変動に応じて直ぐに金利変更が行われ、5年間の据え置き措置も受けられません。
しかも金利上昇率に制限が無いため、上がった分だけ住宅ローン金利も上がることになります。こんなリスクの高い条件で変動金利を選ぶなんてとてもできることではありませんよね。
つまり、金利選択で変動金利を選ぶ場合には必ず元利均等返済を選ばなければならず、元金均等返済を利用できるのは固定金利を選ぶ際のみというのが実情なのです。

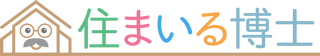

 家を購入する人は要チェック!資金計画書の注意点
家を購入する人は要チェック!資金計画書の注意点
 無理なく住宅ローンを組むため、知っておきたいこと
無理なく住宅ローンを組むため、知っておきたいこと
 都心部で利用者が多い「ペアローン」と「収入合算」の違いを知ってますか?
都心部で利用者が多い「ペアローン」と「収入合算」の違いを知ってますか?
 年収○○円だといくらくらい借りれるの?
年収○○円だといくらくらい借りれるの?
 優遇金利のメリット・デメリットは?適応させるに方法は?
優遇金利のメリット・デメリットは?適応させるに方法は?