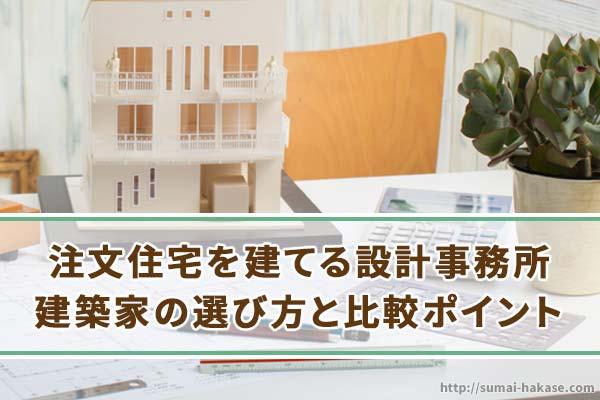
マイホームの新築に向けて、動き出したい。土地は候補がいくつかあるものの、なかなか決定できない。
いろいろと本を読んだりして勉強しているが、家をお願いする先も土地探しと並行して行っている。
そんな中、ハウスメーカーではなく、建築士を探すことになった場合、どのようにして選定していくものか、疑問に思っている方々は多いかと思います。
実際に設計事務所に行ってみたり、コンペに参加してみたり、何をどうすればよいのかわからない方々のために、本記事では設計事務所の選び方をご紹介いたします。
設計事務所の選び方
ハウスメーカーではなく、設計事務所を探す、という選択肢は良い選択だと思います。
土地を自ら探し、希望の土地を考える場合、必ずしもきれいな整形地などにならないことがあります。
その場合、メーカーだと割高あるいは建設不可になることもあります。
設計事務所であれば、コストを考えながら、その土地とあなたにとっての最適解を導いてくれる可能性は高いです。
では、設計事務所のなかでも、どこにお願いをすればよいのか、詳しく解説していきます。
設計事務所を決めるまでの期間
設計事務所を決めるまでには、設計事務所のホームページなどで気にいったところをいくつかピックアップします。
その際に作風や住宅に対する考え方、事務所からの距離なども考慮します。
次に、どの時点から費用が発生するか事前に確認しましょう。
一般的には面談を申し込んでそのあとすぐにプラン作成とはならず、少なくとも面談・相談を経て住まいに対するヒアリングをされた後、プラン検討・作成に入る流れとなります。
この時点で、費用が発生する事務所と1回目のプラン作成は無料の事務所に分かれます。
1回目のプラン提示から費用が発生する場合は、その事情や理由を確認してください。
その上で、事前の面談・相談、その事務所の実例見学などのコンタクトを経て、その建築事務所の作風や住まいの考え方に共感を得られるのであれば、良いでしょう。
このように、建築事務所を決めるためにも、金額面や考え方まで考える必要がありますので、余裕をもって、半年から1年程度選ぶ期間を持つのが無難です。
自分の建てたい家のイメージを固める
設計事務所に家づくりを依頼することのメリットは、完全オーダーメイドの家を建築できることです。
そのため、設計事務所選びを行う上で、予め自分の立てたい家のイメージを固めておくことが大切です。そして設計事務所には、それぞれ得意なデザインがあります。
世間的には非常に評価の高い設計事務所でも、自分のイメージと合わない場合は、やめておいた方が無難です。
実際に設計事務所に相談する前には、その設計事務所の過去の実績を一通り確認して、自分のイメージしているデザインと近い実績があるかどうか確認しておきましょう。
そこのイメージと一致するかを確認するために、予め自分の中で考えを固めておくことが必要です。
建築家との相性が大事
コミュニケーション面での相性はもっとも重要なポイントと言えます。
設計事務所で注文住宅を建てる場合は、打ち合わせの過程だけでも1年近くかかることもあります。意見が合わない建築家との契約は当然さけるべきです。
下記の条件を満たしているか、チェックしてみましょう。
- こちらの話をしっかり聞いてくれているか
- わかるまで面倒がらずに説明してくれているか
- 専門用語を並び立て、何を言っているかわからないことはないか
- できないことはできないと、はっきり言ってくれているか
さらに、家が建った後も相談に乗ってもらうことがあるので、人として長期的に付き合いが可能か、という観点でも見ておくとよいでしょう。
設計事務所の過去の事例を見る
設計事務所が過去に行った設計実績、工事管理実績に関する図面、場合によっては実際の住宅をみせてもらいイメージをつかみましょう。
建築中の住宅を見せてもらうのもよいでしょう。
建築家の監理能力
建築設計事務所の仕事は住宅の設計だけではありません。
工事管理も重要な仕事の一つです。工事管理とは、工事が図面通りに進行しているかを確認することで、建築設計事務所が工事の進行管理を行います。
打ち合わせで自分の要望どおりの設計を提案してもらっても、その通りに仕上がらなければ、意味がありません。
どの程度現場の管理をしてくれる設計事務所なのか確認するために、現場でどの程度の頻度で伺うかを聞いてみましょう。
現場を確認する頻度の目安としては、基礎の配筋~生コン打設の段階で3~5回その他は週に1回程度が平均となりますので、参考にしてください。
依頼する業者を確認する
設計事務所にデザインをお願いした後、どの施工業者へ依頼をするのかしっかり確認しておきましょう。
設計事務所が良い設計をしたとしても、それを隅々まで実現するためには、施工業者の技術も必要となります。
しっかりと現場まで確認をすることが必要となってきます。
色々な設計事務所を見ることが大事
1つの設計事務所に決めてしまわずに、いくつかの設計事務所を見て回り、最も自分のイメージに合う設計事務所を選ぶことが重要です。
手間はかかりますが、これから何十年も住むことになる家ですし、大きな金額が動くお買い物になりますので、手間を惜しまず比較検討すると無難でしょう。
人気の設計事務所(建築家)一覧
それでは、設計事務所を比較する際に重要なポイントについてご説明しましたので、ここからは実際にどのような建築事務所が人気なのかご紹介していきます。
一級建築士事務所アトリエスピノザ
事務所概要
【名称】
一級建築事務所 アトリエスピノザ
【住所】
〒158-0084
東京都世田谷区東玉川2-29-12
コート東玉川201号室
【連絡先】
TEL・FAX:03-6425-9083
E-mail : info@atelier-spinoza.com
建築士プロフィール
井東力 Chikara Ito
【経歴】
- 東京大学建築学科卒業
- エーアンドユー編集
- 堀池秀人都市建築研究所
- 現代建築研究所を経て
- アトリエエスピノザを設立
市原香代子 Kayoko Ichihara
【経歴】
- 武蔵野美術大学建築学科卒業
- 現代建築研究所を経て
- アトリエスピノザ設立
建築実績例
【奥沢の家】
■建築アイデア
敷地は近くにある線路の踏切音や電車の喧噪音が気になる場所にあったため、外観的には、北及び東側(線路側)の前面道路側に閉じて、逆の東南側の中庭に大きく開いて光をそちらから取り入れる構成となっています。この中庭とこれに隣接するリビングを中心に、住宅の多様な空間がコの字状に配置されるコートハウスとなっています。
リビングの中心に吹き抜けを設けることで、開放感が感じられるとともに、1階と2階のつながりができ、どこにいても中庭の緑や光が感じられるようになっています。
また吹き抜けと解して家族がそれぞれの活動の様子や気配を感じられ、愉しく過ごすことのできる住宅となっています。
※アトリエスピノザHPより抜粋(http://www.atelier-spinoza.com/index.html)
ナイトウタカシ建築設計事務所
事務所概要
【名称】
ナイトウタカシ建築設計事務所
【住所】
〒470-0111
愛知県日進市米野木町宮前1-38
【連絡先】
TEL:090-7673-9861
FAX:0561-57-8224
建築士プロフィール
ナイトウタカシ
【経歴】
- 北海道大学建築工学科大学院卒業
- RIA(大手組織設計事務所)
- センスインターナショナル(店舗設計事務所)
- ダグ建築設計事務所を経て
- ナイトウタカシ建築設計事務所 設立
建築実績例
【5人家族のお家】
■建築アイデア
大理石柄のフローリングを採用し、白を基調としたスタイリッシュな家に住みたい、というお客様の希望に応えた。手元隠しのないフルフラットのⅡ型キッチンを提案。見た目もよくて、大きな作業スペースは使いやすさ抜群。
キッチン周りに大容量の食器棚とパントリーを別で設けて、買いだめにも対応可能です。
眺望を最大限取り入れるため、可能な限り大きな窓を計画。そこからテラスにもつながります。
南側から昼間の光を取り入れるため吹き抜け上部に大きなFIX窓を設置して、明るいLDKを実現しました。
リビングの脇に半透明のドアを挟んでキッズスペースを計画。机を設置して、将来そこで勉強できます。
リビングだけでなく、キッチンからもキッズスペースを見通せるので、常に子供のことを感じることができるんです。
※ナイトウタカシ建築設計事務所HPより抜粋(http://www.ntas.info/)
株式会社濱田設計測量事務所
事務所概要
【名称】
株式会社濱田設計測量事務所
【住所】
〒572-0848
大阪府寝屋川市秦町1-3
【連絡先】
TEL:072-823-7935
FAX:072-825-1287
建築士プロフィール
濱田猛
【経歴】
- 法政大学工学部土木工学科卒業
- 京都工芸繊維大学大学院
- 工芸科学研究科造形工学専攻修了
- 株式会社コンパス建築工房を経て
- 株式会社濱田設計測量事務所 設立
建築実績例
【狭小敷地、ローコスト住宅】
■建築コンセプト
大阪府枚方市の閑静な住宅地にシンプルな木造2階建の住宅を設計しました。周囲の住宅からの視線をカットしつつ、明るい光を十分に取り入れるため、家の中心となるリビングに大きな吹き抜けを設けました。
その吹き抜けの中に大小さまざまな窓をちりばめ、午前中~夕方にかけていろんな窓から光が差し込む空間としています。
1Fはキッチンを中心としたワンルーム空間で、リビングからダイニングキッチンまで斜めに視線が抜ける計画です。狭小地の住宅で広さを感じる演出をしています。
リビング吹き抜け部分の壁には、シナベニヤを鎧貼りとし、大きな木の壁をつくりました。
リビング、ダイニング、キッチン、階段を通した家のいろいろなところからこの大きな木の壁を望むことができます。
※株式会社濱田設計測量事務所HPより抜粋(http://hamada-design.com/)
株式会社プライム一級建築士事務所
事務所概要
【名称】
株式会社プライム一級建築士事務所
【住所】
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-10-10-4F
【連絡先】
TEL:03-3354-8204
FAX:03-3354-3745
建築士プロフィール
西島正樹
【経歴】
- 東京大学建築学科卒業
- 東京大学大学院建築学専攻修士課程修了
- 株式会社石本建築事務所を経て
- 株式会社プライム一級建築士事務所 設立
建築実績例
【光を抱く家】
■建築アイデア
夫婦+成人した子供2人のための家。大人4人の住まいとして、寝室、個室、書斎などの個のスペースが、共有の場であるリビングダイニング空間に対して、十分な距離と適切な位置関係をもつことが大切と考えた。
そこで建物を大きく3つに分け、中央を共有の場、南と北にそれぞれ寝室などの個室空間を配置した。
そして南、北の個室と中央のLDとの間に、空からの光に輝く明るいつなぎのスペース(階段・サンルーム)を挟み込むことで、各個室が「離れ」のような独立した感じを持つようにした。
個室が「離れ」のような独立した感じを持つようにした。個室の独立感が高まり、落ち着く一方部屋を出て、外部のような空間を通るうちに、自ずと心が解き放たれればと考えた。
中央のボリュームは、南が庭、北側がトップライトに輝く階段につながる開放的なリビングダイニングとし、その上に夫婦それぞれの書斎・ワーキングスペースを背中合わせで配置した。
夫の書斎は、閉じた部屋にして、そこからロフトに上ると、建物の一番高い場所から全体を見下せるようにした。
一方、妻のワーキングスペースは、リビング吹き抜けに面した建物の中心に開放的に配置し、いつも建物全体の気配を把握できるようにした。
機能に応じて配置された各スペースを、間に挟み込まれた光のスペースが分かち、つなぐことにより個と全体とが際立ちつつ、結び付きあう建築空間を目指している。
※株式会社プライム一級建築士事務所HPより抜粋(http://www.prime-arc.com/)
片桐寛文建築研究所2
事務所概要
【名称】
片桐寛文建築研究所2
【住所】
〒191-0031
東京都日野市高幡1009-7 TIKビル704
【連絡先】
TEL:042-506-7832
FAX:042-506-7852
【経歴】
工学院大学工学部卒業
片桐寛文建築研究所2 設立
建築実績例
【KUMO】
■建築アイデア
15枚の「外側へ張り出した壁」の角度により、内部をパブリックとプライベートゾーンに分け、間仕切りに頼らず、公私分けができるよう計画しています。また、太陽と影によるコントラストが室内をすごしやすくするとともに、周辺からの視線を程よく遮ります。
1階南側の庭は、地面に敷き詰めたタマリュウ上を子供たちがハダシで遊びまわるだけでなく、緑化によりヒートアイランド現象を抑制します。
そして外部との緩衝帯になり室内を開放的にさせ「大地」を感じる場所としました。
2階にはLDK、和室、水回り、これらとつながるような僕それぞれにバルコニーを配置しました。
片流れの屋根を活かした勾配天井・高窓から見える空・バルコニーの先の風景・空とが一体となるよう、視界が周辺の大地から切り離され、空の中にあるように計画しています。
2階からペントハウスへ上がると、回廊を通って屋上へ出れます。屋上は北斜面地同様北側に開いた階段状。
それを上下すると空を回遊し、大気を感じながら空中を楽しむことができます。また地平線を想像させ、地球の際が丸くなっている風景をみることができる四方に大きく広がった外部空間です。
この住宅は、大気を感じられる1階から、雨露が蒸発するように2階へ上昇し、2階と屋上は気化した水分が、雲ごとく空に溜まる。
そんな感覚で人間が行動する動線計画から、空間が宙に浮いた様な建築です。
雲のように空から地上を眺め、地球に被さる「大気」という大屋根の下、あらゆるもの(植物・動物・その他)が地球上に寄り集まって生きていること、
世界は切れずに繋がっていることを意識させ、他を思い周りを豊かにする人が育ってほしい。
※片桐寛文建築研究所2HPより抜粋(http://www.katagirikanbun.com/)
建築設計事務所にマイホーム建築をお願いするとき、より自分の理想にあった家を建てたい、と思います。
建築士の腕が如実に反映されますので、設計事務所選びが非常に重要となってきます。画一的な設計ではないためです。
より自分に合った設計事務所を選び、より自分の理想に近い家を建てるために、この記事が読者の方々のお役に立てれば幸いです。

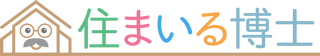

 注文住宅VS建売住宅 費用・デザイン・保証の3つで比較!
注文住宅VS建売住宅 費用・デザイン・保証の3つで比較!
 こんなことまで!?決めごとが盛りだくさんの注文住宅
こんなことまで!?決めごとが盛りだくさんの注文住宅
 注文住宅を建てる際のハウスメーカー選びのコツ
注文住宅を建てる際のハウスメーカー選びのコツ
 マイホームへの第一歩!宅地の決め方選び方
マイホームへの第一歩!宅地の決め方選び方
 土地を買う前にここは押さえておきたいポイント!
土地を買う前にここは押さえておきたいポイント!