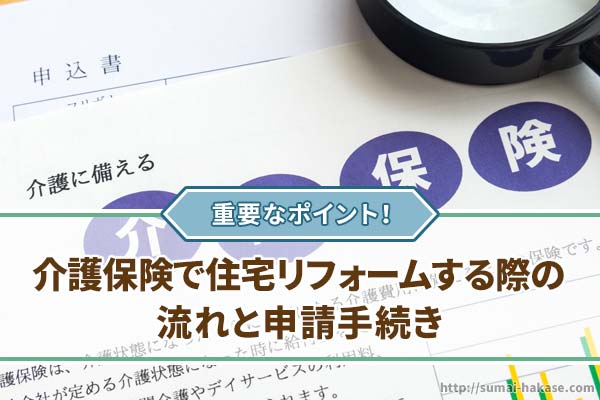
介護保険で要支援や要介護に認定された人との同居においては、住宅にもそれなりの改修が必要になってきます。そんな時に是非とも利用してもらいたいのが、介護保険の住宅改修費の支給制度です。
介護保険で要支援や要介護の認定者が暮らしていく上で心身の状況と住宅状況に鑑みて、住宅改修が必要であると認められた場合、介護保険制度により住宅改修費の支給を受けることができます。
しかし、住宅改修費の支給を受けるには着工前の事前申請が必要となり、その適用方法にも様々な決まりがあります。
そこで今回は住宅改修費の支給を受ける際の流れと申請手続きについてわかりやすく解説していくことにします。
住宅改修費の支給内容
それでは本題に入る前に住宅改修費の支給内容について簡単に紹介しておきましょう。
その内容は下記のとおりです。
- 受給対象者 要支援1・2、要介護1~5の認定者
- 対象住宅 要支援1・2、要介護1~5の認定者が居住している住宅
- 利用限度額 最大20万円(自己負担1割のため、実質最大18万円)
利用限度額20万円に達しない場合には、その利用範囲内において何度でも支給を受けることができますが、基本的には20万円の支給を受けた時点で支給を受ける権利はなくなり、再利用をすることはできません。
しかし、下記条件においては再利用が可能となるので、その利用条件はしっかりと覚えておきましょう。
- 被保険者が住宅を転居した場合
- 被保険者の要介護状態が3段階以上重くなった場合
介護保険で住宅リフォームを行う際の手順
介護保険制度で住宅改修費の支給を受けられるといっても、どこになにをどうすればいいのかわからないという人が大半でしょう。要介護の認定を受けると十分な介護サービスを受けられるようケアマネージャーが付き、下記のようなサポートをしてくれます。(*要支援の場合には地域包括支援センターが担当となる)
- 居宅で受けられる介護サービスの紹介
- ケアプランの作成
- サービスの調整
- サービス給付費の計算と請求
よって、住宅改修費の支給を受ける場合には、まずは担当ケアマネージャーに相談するのが一番の近道となります。
下記が住宅改修費の申請手続きの流れです。
- 住宅改修の相談・検討
- 介護保険課への事前申請
- 事前申請確認書兼完成届出書の交付
- 住宅改修の着工
- 介護保険課への事後申請
- 住宅改修費の支給
それではこれら流れに添って、各内容について注意点等を解説していきましょう。
1.住宅改修の相談・検討
住宅改修の相談は要介護者ならば担当ケアマネージャー、要支援者ならば地域包括支援センターが窓口となります。住宅改修を着工する前に必ず担当者に相談し、改修業者を交えて住宅改修費の支給を受けるのに必要となる提出書類の作成を依頼しましょう。
住宅改修費は着工前に事前申請が必ず必要となります。事前申請なしに着工した回収工事では住宅改修費の支給を受けることはできません。くれぐれもこの点は注意するようにして下さい。
住宅改修費支給の対象となる住宅改修
住宅改修は何でも住宅改修費の支給対象となるわけではありません。住宅改修費の支給対象となるのは下記の住宅改修です。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 床や通路の床材の変更(滑り防止、および移動円滑化のため)
- 扉の取替え
- 洋式便器等への取替え
- 各改修工事に付帯する工事
各改修工事の詳細内容については、担当ケアマネージャーおよび地域包括支援センターに相談すれば詳細な内容を教えてくれます。希望する改修工事が住宅改修費の支給対象となるかを確認するようにしましょう。
2.介護保険課への事前申請
住宅改修工事に着工する前には、下記書類を市の介護保険課に提出し事前申請する必要があります。
- 住宅改修費事前確認書、および支給申請書
- 住宅改修が必要となる理由が書かれた理由書
- 改修工事見積書
- 改修箇所の工事前写真(日付入りのもの)
- 住宅平面図
- 住宅改修承諾書(改修する住宅が被保険者以外の所有となっている場合)
- 委任状(被保険者以外の口座へ振込希望の場合)
提出に必要となる書類に関しては「住宅改修が必要となる理由が書かれた理由書」のみ担当ケアマネージャーらが作成してくれますが、ほかの書類に関しては申請者が用意することになります。工事関連の書類は施工業者に依頼するのが一番ですが、まずはどうすればいいのかを担当ケアマネージャー等に相談するようにしましょう。
3.事前申請確認書兼完成届出書の交付
介護保険課に提出した書類に不備がなければ、住宅改修が完成した後に提出する事前申請確認書兼完成届出書が交付され、住宅改修に着工できる状態となります。
先程も言いましたが、住宅改修に着工するのは事前申請確認書兼完成届出書が交付されてからです。交付前の着工となれば住宅改修費の支給は受けられないので十分に注意するようにして下さい。
4.住宅改修の着工
住宅改修の着工時には覚えておいてもらいたい下記注意点があります。
- 被保険者が病院や施設に入っている場合
- 着工後に工事内容に変更が生じた場合
それではこれら注意点に関して簡単に解説しておきましょう。
被保険者が病院や施設に入っている場合
要介護・要支援の認定者である被保険者の住所が改修工事の住居であっても、現在、病院や施設に入っており居住していない状態だと住宅改修費は支給されません。もちろん申請もできますし、支給を受ける権利はあるのですが、支給を受けられるのは被保険者が居住していることが条件となります。
よって、申請している住宅改修費の支給は居住が開始されてからとなり、仮に病院や施設から帰れないという状況となった場合には住宅改修費の支給は受けられません。
着工後に工事内容に変更が生じた場合
着工後に予期せぬ事態から施工場所や使用材料等に変更が生じた場合には、直ちに工事を中断し、その旨を介護保険課に連絡しなければなりません。状況に応じては見積書等の再提出が必要になるので、必ず工事を中断し連絡するようにしましょう。
工事を中断せずに連絡のないまま内容変更となったまま改修を行った場合、住宅改修費の支給は受けられなくなってしまいます。
5.介護保険課への事後申請
住宅改修が完成後には介護保険課への下記書類の提出が必要になります。この書類提出をもって申請完了となるので、必ず忘れないよう提出しましょう。
- 事前申請確認書兼完成届出書
- 領収書(被保険者宛で原本を提出)
- 請求明細書(被保険者宛でコピー可)
- 改修箇所の工事後写真(日付入りのもの)
この提出書類に不備があれば住宅改修費の支給が遅れるので、不備がないかを担当ケアマネージャー等に確認してもらうことをおすすめします。
6.住宅改修費の支給
介護保険課への事後申請に不備がなければ郵送にて被保険者宛で「支給決定通知書」が送られ、住宅改修費の支給は指定された口座へ事後申請した月の翌月末日に振り込まれます。
まとめ
住宅改修費は最大で20万円、そのうち1割が自己負担となるので決して大きな補助となるわけではありませんが、介護保険制度に定められた被保険者の権利の1つです。住宅改修が必要な場合には是非とも利用してもらいたい制度と言えるでしょう。
申し込みに関してもほかの補助金や控除に比べ担当ケアマネージャー等の力添えが期待できるので、比較的簡単に申請できます。申請時には担当ケアマネージャー等によく相談し、できる限り自己負担の少ない住宅改修とするようにして下さい。

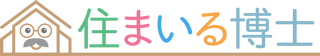

 キッチンのリフォームで一番注意すべきこと
キッチンのリフォームで一番注意すべきこと
 外壁リフォーム前に知っておくことまとめ~相場費用・時期の目安
外壁リフォーム前に知っておくことまとめ~相場費用・時期の目安
 水回りのリフォームにかかる相場費用と注意点まとめ
水回りのリフォームにかかる相場費用と注意点まとめ
 増築リフォームで間取りを変更する時の相場費用と注意点まとめ
増築リフォームで間取りを変更する時の相場費用と注意点まとめ
 バスルームリフォームで注意すべきこと
バスルームリフォームで注意すべきこと